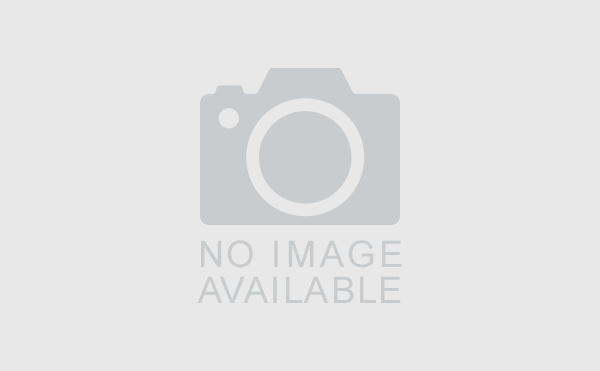商標を取るための費用についてサクッと解説します
特許庁に出願をして「商標登録」を受けるまでにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?商標登録を受けるまでには大きく以下のステップがあります。
- 先行商標調査
- 出願
- 拒絶理由通知への対応
- 登録査定に対して登録料の納付
この中で、特許事務所に支払う費用と特許庁に支払う法定費用がそれぞれ必要になってきます。
1.先行商標調査
先行商標調査とは、自社の社名やブランド名、ロゴなどが商標登録を受けられるかどうかを判断する調査です。出願しようとしている商標と似た商標がすでに登録されていないかどうかを、特許庁が公開しているJ-PlatPatというデータベースを使いご自身で検索することもできますが、漏れなく適切な調査を行うことは非常に難しいため、やはり専門家である弁理士に最終的な先行商標調査を実施してもらう方が良いです。
日本弁理士会が実施した平成15年及び18年の弁理士報酬のアンケートによれば、出願前に行われる文字商標調査の一般的な弁理士報酬(特許事務所に支払う手数料)は、1商標1区分で約20,000円、通常複数の区分を選択して出願することが多いですので、仮に区分が3つだとすると60,000円の費用がかかります。
なお、すまるか(URLにリンク)であれば、クラウド上に構築したAI+RPAシステムによる半自動化により、調査報告書の作成効率を追求しているため、先行商標調査の費用は無料です。
2.出願
商標登録出願では、特許事務所に支払う法定費用と、特許事務所の弁理士に支払う手数料が必要です。
なお、ご自身で出願した場合は特許事務所に支払う手数料は掛かりませんが、適切でない願書を提出してしまった場合、補正指令や拒絶理由通知を受け、適切な権利を取得できなかったり、商標登録が受けられなかったり、再度お金を払って出願しなければならないといったリスクがありますので、専門的な知識のある弁理士に依頼することをおすすめします。
特許庁の法定費用は、3,400円+(区分数×8,600円)です。
例えば、1~5区分を出願した時の特許庁法定費用は、
- 1区分:12,000円
- 2区分:20,600円
- 3区分:29,200円
- 4区分:37,800円
- 5区分:46,400円
となります。
また、特許事務所の弁理士に支払う出願手数料は、上で記載した日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートによると、1区分で平均約67,000円です。
なお、すまるか(URLにリンク)であれば、クラウド上に構築したAI+RPAシステムによる半自動化により、出願願書の作成効率を追求しているため、出願手数料が1区分当たり12,000円(税別)という非常に安価な価格での出願が可能です。
すまるかの費用はこちら
3.拒絶理由通知への対応
商標登録出願後、特許庁の審査官により審査がなされます。特許庁の審査官により、商標や保護を受けようとする指定商品・役務(サービス)の記載に問題があると判断された場合には、拒絶理由通知が送付されます。
よく来る拒絶の理由としては、大きく以下の3つがあります。
- 出願した商標に似た先行商標が存在する場合
- 出願した商標が、一般名称・慣用名称・商品等の品質を普通に表したに過ぎない商標等に該当し識別力が無い場合
- 願書に記載した指定商品又は役務に不備がある場合
これらの拒絶理由が通知された場合には、願書に記載した指定商品又は役務の記載を修正する補正書を提出したり、先行商標と似ていない又は識別力があるといった反論を意見書に書いて提出する必要があります。拒絶理由通知に応答せず放置すると、拒絶理由が解消しないものとして拒絶査定が送達され、商標登録を受けられないという結果となってしまいます。
拒絶理由通知に対する応答には、原則特許庁の法定費用は掛かりません。一方、商標法や施行規則、審査基準に沿った形で説得力のある意見書や補正書を作成し、無事商標登録を勝ち取りたいのであれば、専門的な知識が不可欠です。登録の可能性を高めるためにも専門家である弁理士に依頼する方が良いでしょう。この場合の特許事務所の弁理士に支払う手数料は、上で記載した日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートでは、1区分で補正書の作成・提出が平均約41,000円、意見書の作成・提出が平均約48,000円です。出願する区分が増えたり反論の難易度が高くなった場合には、手数料は高くなります。
例えば、よくある拒絶理由の1つである「商標・商品ともに似た先行商標・商品が存在している」という拒絶理由通知に対して、似ている一部の商品を削除する補正と他の商品については先行商標と似ていないという意見書を作成・提出した場合には、上記アンケートの平均値では合計89,000円の弁理士費用がかかることになります。
なお、すまるか(URLにリンク)では、難易度に応じて料金表に記載のオプション反論料金がかかりますが、単純に一部の商品・役務を削除する補正とその旨の意見書を提出するだけであれば、合計で2万円(税別)の費用で対応しております。
4.登録査定に対する登録料の納付
拒絶理由通知が来ることなく登録査定となった場合、若しくは、拒絶理由通知に対して提出した意見書・補正書の反論が認められ登録査定となった場合、登録査定謄本の送達から30日以内に登録料を支払うことで、正式に商標登録を受けることができます。
登録料の納付は、特許事務所に支払う法定費用と、特許事務所の弁理士に支払う手数料が必要です。
特許庁の法定費用は、5年間保護を受ける場合で17,200円×区分数です。10年間の保護を受ける場合には、32,900円×区分数の費用が必要となります。
5年分を2回納付するよりは、一括で10年分の費用を納付する方が総額は安くなりますが、区分数が増えるにつれ最初に支払う金額が大きくなるので、事業が10年以上安定して続きそうかどうか、現在手持ちの事業資金が十分にあるかどうか、を考慮し、5年分納付にするか10年分納付にするかを決めるとよいでしょう。
なお、5年の場合でも10年の場合でも、期限満了前に次の期間の更新登録料を支払い続ける限り、何度でも永遠に商標登録を更新し続けることが可能です。
特許事務所の弁理士に支払う登録料納付手数料は、上で記載した日本弁理士会が実施した弁理士報酬のアンケートでは、1区分で平均約45,000円です。
すまるか(URLにリンク)では、クラウド上に構築したAI+RPAシステムによる半自動化により、登録料納付書面の作成効率を追求しているため、登録料納付手数料は1区分当たり税込17,800円という非常に安価な価格に設定しています。
特許庁に登録料を納付した後には、2週間程で商標登録となり、商標登録番号が付与されます。また登録料納付から3週間程で、商標登録証という賞状のようなものが代理人弁理士宛に送付されます。
代理人である弁理士は、受領した商標登録証を、依頼者宛に郵送することで、商標登録の手続きが完了します。
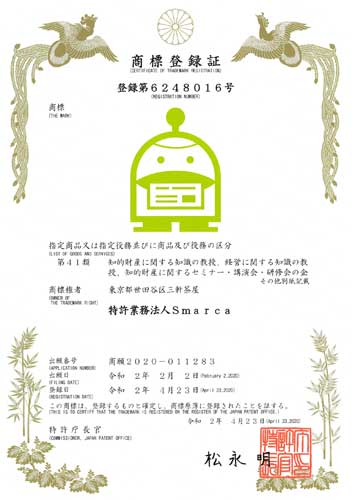
5.結局いくらかかるのか?
以上説明しました費用をまとめると、
例えば1区分の場合、一般的な特許事務所の場合
- 先行商標調査時に22,000円(税込)の弁理士費用
- 出願時に12,000円の特許庁法定費用+73,700円の弁理士費用=85,700円(税込)
- 登録料納付時に17,200円の特許庁法定費用+49,500円の弁理士費用=66,700円(税込)
の合計、税込174,400円(一般的な特許事務所の料金)
もしも拒絶理由通知が来た場合には、更に反論費用として97,900円(税込)の費用が必要です。
一方、すまるかでは、AI+RPAにより費用を抑えておりますので、
- 先行商標調査は無料!
- 出願時に12,000円の特許庁法定費用+13,200円の弁理士費用=25,200円(税込)
- 登録料納付時に17,200円の特許庁法定費用+17,800円の弁理士費用=35,000円(税込)
の合計、税込60,200円(すまるかの料金)
もしも拒絶理由通知が来た場合には、更に反論費用として約22,000~55,000円(税込)程度の費用がかかります。 上で説明しました通り、日本弁理士会の統計によれば、「すまるか」は一般的な特許事務所の費用の1/3程度の金額で権利取得が可能となりますので、まずは是非、無料調査を実施してみてください。
商標が取れそうかどうかの調査は無料です。
よくある質問一覧に戻る